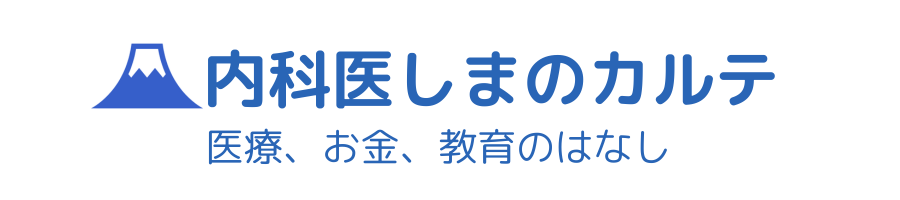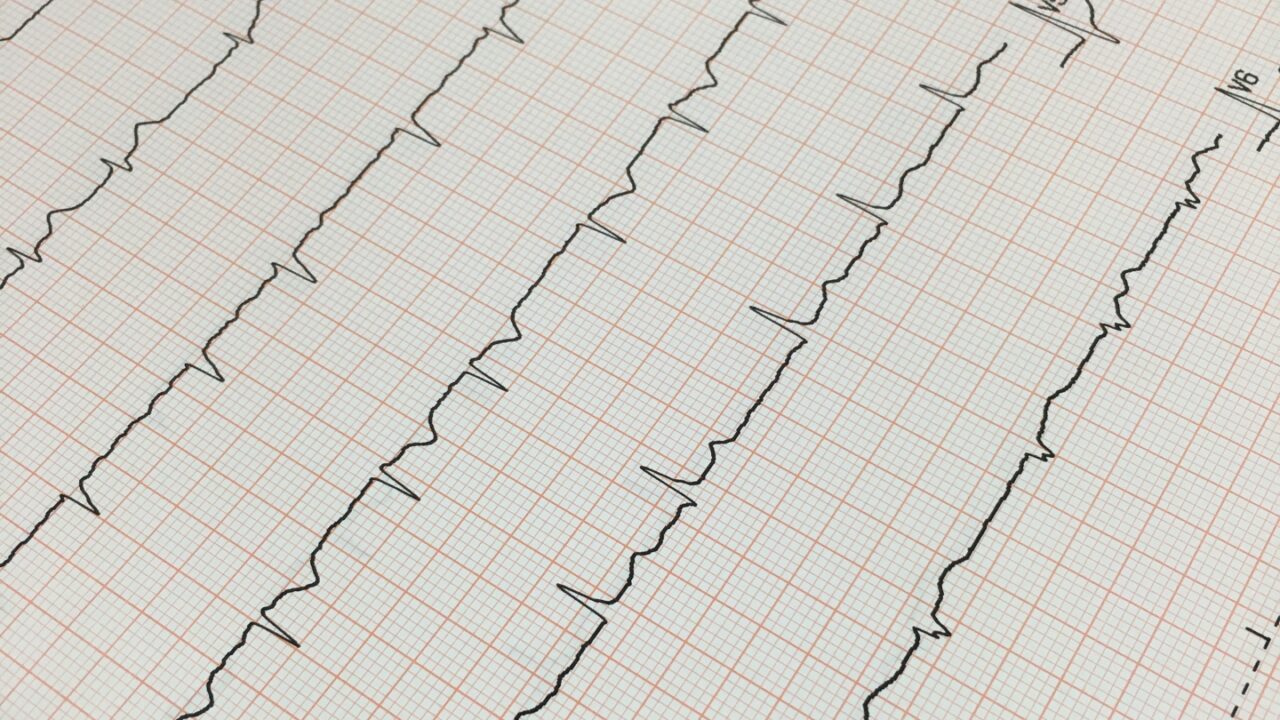病院や健診で心房細動(しんぼうさいどう)と言われた、またはApple Watchで心房細動の波形が出たけど、どういうことなのか分からない方は多くいらっしゃいます。
ここでは心房細動という病気について、原因・症状・治療についてご説明いたします。
心房細動とは?
正常の心臓では、心房(しんぼう)と心室(しんしつ)が1:1で規則正しく収縮しています。
しかし、心房細動では、心房が細かく不規則にふるえるようになり、脈が乱れ、1拍1拍バラバラになります。
心房細動の原因
肺静脈からの上室期外収縮
左心房(さしんぼう)という心臓の左上の部屋には、肺からの血液が心臓に流れ込むための肺静脈(はいじょうみゃく)という血管がつながっています。
肺静脈から心房細動の引き金となる異常な電気刺激が発生し、心房にそれが伝わることで、心房が細かくふるえるようになり、心房細動が発症するとされています。
異常な電気刺激は、上室期外収縮(じょうしつきがいしゅうしゅく)と言われます。
心房細動の原因となる上室期外収縮はほとんどが肺静脈から発生しますが、それ以外の場所からも発生することがあります。
内科疾患
心臓病と心房細動が関連したり、その他の病気から引き起こされることがあります。
生活習慣
アルコール、タバコ、肥満によっても起こるとされています。また加齢による心房の変化の影響が大きいと言われています。
心房細動の症状
心房細動になると、脈が乱れてバラバラになり、速くなります。
動悸、胸の不快感
息切れ、疲れやすさ、めまい、ふらつき
ただし、無症状なこともあり、健康診断で初めて指摘されることもあります。
どうして怖い?脳梗塞リスクについて
心房細動では、心房内の血流がよどんでしまい、血栓(けっせん)と言われる血の塊ができやすくなります。
CHADS2 score(チャッズ ツー スコア)という点数表で脳梗塞のリスクを計算できます。
これは心不全(Congestive heart failure)、高血圧(Hypertension)、年齢(Age 75歳以上)、糖尿病(Diabetes Mellitus)、脳卒中または一過性脳虚血発作(Stroke or TIA)の頭文字をとったものです。
点数が高いほど、脳梗塞のリスクも高くなります。
| 心不全 | 1点 |
| 高血圧 | 1点 |
| 年齢 | 1点 |
| 糖尿病 | 1点 |
| 脳卒中または一過脳虚血発作 | 2点 |
抗凝固療法(こうぎょうこりょうほう)と言われる、血液をサラサラにする薬は、CHADS2 score 1点以上で始めることを推奨しています。
診断方法
心電図
確定診断は心電図で行います。
症状だけでは診断ができないため、動悸や胸の不快感があるときに心電図を行うことが必要です。
症状がない場合は、健康診断で偶然見つかることが多いです。
ホルター心電図
ホルター心電図は1日中心電図を着けてもらい、1日の中でどれだけ不整脈が起きたかを診断する検査です。
入院の必要はなく、外来で行います。
また1週間連続して記録できる、長時間ホルター心電図もあります。
Apple Wacthの心電図アプリ、携帯型心電計
動悸の頻度が数か月に1回などの場合は、ホルター心電図でもなかなか診断がつかないこともあります。

それ以外には、オムロンなどから発売されている携帯型心電計が有効です。
これは症状が出たときのみ使用し、自宅で心電図の記録ができる機械です。
治療
抗凝固療法
心房細動の合併症として重症になるのは、脳梗塞です。
そのため、心房細動と診断された場合、まずはCHADS2 scoreでリスクを計算します。
1点以上なら抗凝固療法を開始します。
血液をサラサラにする薬のことを、抗凝固薬(こうぎょうこやく)といいます。
抗凝固薬を定期的に内服してもらうことを、抗凝固療法といいます。
リズムコントロール
心房細動を正常の脈(洞調律)に戻す治療をリズムコントロールといいます。
①抗不整脈薬(こうふせいみゃくやく)を内服する。
②カテーテルアブレーションを行う。
まずは抗不整脈薬を使用して、正常に戻らなければカテーテルアブレーションを行います。
入院期間は3~4日程度で、退院後の生活も入院前とほとんど変わらず過ごすことができます。
レートコントロール(心拍数調整)
レートコントロールは、心房細動はそのままにしておき、心拍数だけ調整する治療です。
脈をゆっくりにする薬を飲むことで、心房細動ではあるけど、脈が速くならないようにします。
まとめ
心房細動は適切に治療すれば、日常生活にも支障なく過ごせる病気です。
ただし、症状ないからと言って放置しないことが大切です。
脳梗塞にならないためには、抗凝固療法が必要となってきます。
またカテーテルアブレーションなどの治療も進化しています。
症状があれば、病院を受診しましょう。